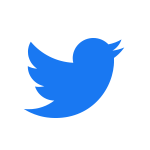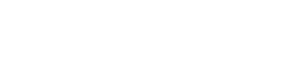2025.08.26
NEWSアカデミアとスタートアップ企業を行き来する 臨床・研究・企業・教育、多様な道をつなぐ医師のキャリア TXP Medical CSO 後藤 匡啓/ 横浜市立大学学術院医学群 教授
横浜市立大学学術院医学群、ヘルスデータサイエンス専攻教授の後藤先生は教鞭をとる研究者としての側面だけでなく、TXP Medical株式会社の執行役員兼最高科学責任者を務めています。後藤先生はアカデミアと産業界の双方で活躍する稀有なキャリアを持ち、医療データの活用と社会実装を推進しています。主にヘルスサービスリサーチ(医療政策・医療経済を含む医療の質やアクセス・コストを評価)を担当し、最前線の実装知と、アカデミックなエビデンス創出を両輪で推進しています。
TXPにおいても、研究者としての知見を活かしながら、研究チームを統括。構造化カルテ、搬送データ、検査値など多様な実臨床データを活用した医療の質評価モデルの構築や、行政・アカデミアとの共同研究をリードし、「医療データサイエンス」の新たなモデルを体現しています。
そんな後藤先生にインタビューを行いました。
1. 多彩なキャリアのはじまり──救急医の問題意識が導いた研究者の道
私は2008年に、福井大学医学部医学科を卒業し、ER型救急医として臨床の現場に立ち始めました。日々多様な症例と向き合う中で、治療判断における科学的根拠の乏しさや、高齢化に伴う救急医を含む医療従事者への負担増加といった構造的な課題を肌で感じていました。
このような課題意識を抱くなか、研究メンターである長谷川耕平先生(現・ハーバード大学医学部教授)から誘いを受けたことをきっかけに、臨床研究を体系的に学ぶべく、アメリカへの留学を決意しました。渡米後は、言語の壁とハイレベルな研究環境に直面し、成果を出すことができずに苦悩する日々が続きました。それでも、ハーバード大学公衆衛生大学院・マサチューセッツ総合病院救急部で学ぶことで、主に呼吸器や感染症領域におけるヘルスサービスリサーチの論文を数多く出版し、また2016年には米国救急医学会学術総会において最優秀演題賞を受賞することができました。
帰国後は東京大学大学院にて、臨床疫学・医療経済学を中心とした、日本の医療ビッグデータ研究に取り組みました。しかし、やがて「既存のデータベースの分析だけでは、真に解決すべき臨床課題に迫ることができない」「現場で最も重要な救急医療の負担軽減には、そもそも必要なデータが存在しない」といった、研究限界に直面していきました。
2. TXPでの挑戦──企業だから生み出せる価値、アカデミアだから伝えられる意義
このような研究上のジレンマを抱えていた折に出会ったのが、TXP Medical株式会社でした。“医療データを構造化し、医療データで命を救う”という同社のビジョンが、これまで抱いてきた問題意識と見事に重なっていたのです。「データを生み出すビジネスと、それを活用する研究の接点にこそ、新しい価値があるのではないか」と考えたこと、また同時にアカデミアの道を選ぶつもりが急に無くなったこともあり、同社への参画を決意しました。
とはいえ、当時は医師がスタートアップへ転職することは一般的ではなく、「ハーバードまで行って、なぜスタートアップへ?」という声もありました。実際、しばらくの間は私自身も「自分はTXPの社員です」と胸を張って言うことができなかった時期もありました。
それでも、研究への強い情熱を共有する社長をはじめ、志高く優秀な仲間たちに支えられ、成果を積み重ねていく中で、次第に自分の決断に確信を持てるようになっていきました。当時はリスクに見えた選択が、結果として社会のニーズに合致したことでオリジナルなキャリアを積み重ねることができたと実感しています。
3. アカデミアと企業──両方に片足を置く
TXPでは最高科学責任者として、臨床研究に携わってきた経験を活かし、TXPが開発・提供しているシステムの実装とその評価、社内リサーチチームでの臨床研究の指導・統括・支援、そして若手研究者の育成に取り組んでいます。TXPに参画してよかったと思うことは、優秀なメンバーが集まっていることで、私自身もメンバーから刺激を受けています。
一方で、TXPに勤めて4年、自分が44歳の時に当時客員講師だった横浜市立大学大学院ヘルスデータサイエンスから教授の公募が出ました。もともとアカデミア志向が強かったのもあり、知人にも相談したところ「このタイミングを逃したら、一般企業からアカデミアに戻る機会はなくなるのでは?」とアドバイスをもらったこともあり応募しました。幸いにも縁をいただき、今はヘルスデータサイエンスの教授として、新たな一歩を踏み出しています。
大学教授と企業の執行役員という両立が難しい二つの立場を兼務することは、制度的な制約も多く、極めて稀なキャリアパスです。教授選考の過程では、TXPでの職務との両立について厳しいご指摘もいただきました。しかし、アカデミアの世界だけでは十分な社会実装に至らないという課題を実感しており、TXPで培ってきた経験や、共に歩んできたチームの存在は欠かせないものでした。それらの経験や繋がりも含めて評価されたものと思っています。
4. 今後の展望──アカデミアと産業界の融合が生み出す未来
これから医師が産業界に関わるキャリアパスは増えていくでしょう。とはいえ、その多くは臨床医を本業とし、企業活動は副業的に関与する形になるだろうと考えています。 従来、医師のキャリアは臨床または研究に限定されがちでしたが、今後は「企業で働く」という選択肢を現実的に捉える若手医師も増えていくのではないでしょうか 。
私は、「本質的な自己成長を求める優秀な人材は、同様に成長意欲の高い環境を求める」と考えています。実際に、TXPでは定期的な勉強会を継続しており、こうした場を通じて互いに学び合い、アカデミアと産業界の動向をリアルに把握できることに価値を見出すメンバーが多く残っています。
今後のキャリアにおいては、「アカデミア」と「産業界」の両軸を軸に据えながら、いくつかの重点分野に注力していきたいとの思いがあります。企業としては、リサーチチームの機能強化、医療情報の標準化、救急データの統一化と調査体制の構築、さらには将来的な上場準備などが課題となります。
「日本の救急医療の実態を、データで可視化できるのはTXPしかない」という志のもと、今後も社会に向けて救急領域の重要データを発信していくことが使命だと考えています。私自身は、5年ほどでデータ収集・解析の基盤が安定すれば、次世代へのバトンタッチを検討したいです。以後は、教授職としてのキャリアを深化させるとともに、医療政策への関与や、国際的テーマにも取り組んでいきたいです。
5. 教育者として──若手へのメッセージとキャリア観
教育は私のライフワークの一つであり、人材育成に情熱を注いでいます。研究指導のみならず、学位取得支援や、研究満足度の高い環境づくりを大切にしています。若い世代に伝えたいのは、「何よりも、自分が“楽しい”と思えることを軸にしてほしい」ということです。
その軸を見失ってしまうと、後々『自分の人生は何だったのか』という後悔につながりかねません。だからこそ、キャリアは自分で決めるべきです。他人に与えられた道では後悔する可能性があるけれど、自分で選んだ道なら納得できるはずです。
今後も、大学教授とスタートアップCSOという二軸を活かしながら、アカデミアと産業の橋渡し役として独自のキャリアを切り拓いていきます。
後藤先生のキャリアは、“次世代型医療人材”の理想像を体現しています。救急医・臨床研究者・スタートアップCSO・大学教授──その一見バラバラに見える肩書きはすべて、「データで命を救う仕組みをつくる」というビジョンのもとに統合されています。スタートアップへの挑戦、アカデミアへの回帰、そして両方の立場を横断し続ける柔軟なキャリア形成。後藤先生の選択の連続は、他の誰とも異なる“唯一無二のキャリア”を築いてきました。これからも、臨床と研究、産業と社会をつなぐプレイヤーとして、後藤先生は日本の医療の発展と医療人材育成を目指しています。
参考サイト
●Coffee doctors インタビュー記事
後藤 匡啓 | coFFee doctors - ドクターズ
●医学書院 多様化する医師のキャリアプラン
多様化する医師のキャリアプラン(後藤 匡啓,三澤 園子,矢吹 拓,鎌形 博展) | 2025年 | 記事一覧 | 医学界新聞 | 医学書院
●横浜市立大学 データサイエンス研究科 ヘルスデータサイエンス専攻 教員紹介
後藤 匡啓/ GOTO Tadahiro | 教員紹介 | ヘルスデータサイエンス専攻 | YCU 横浜市立大学 データサイエンス研究科